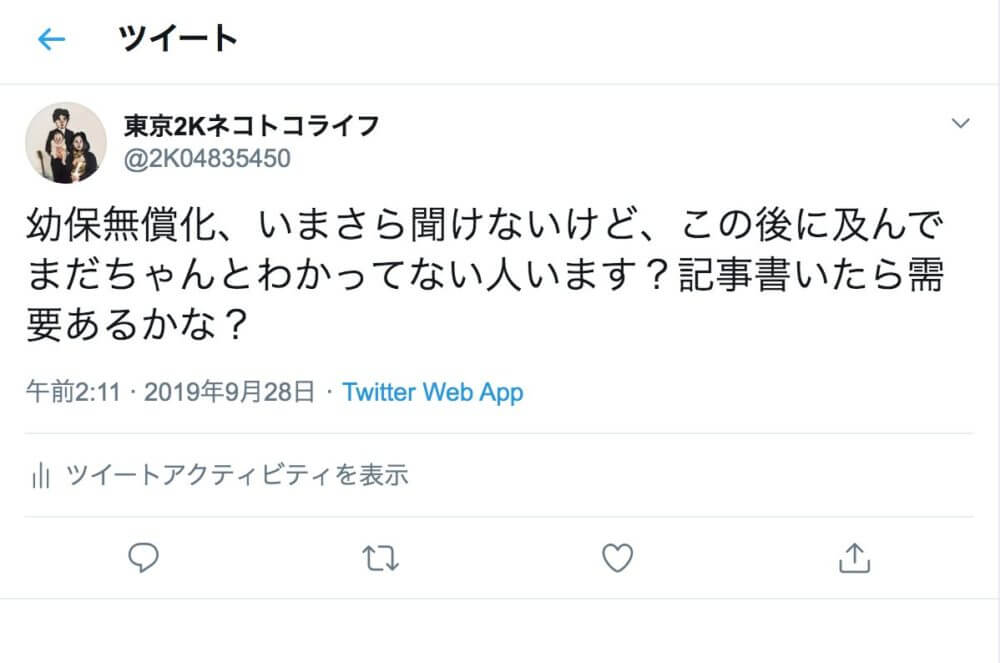
10月からスタートする幼保無償化とは?
2019年10月1日からいよいよ始まる幼保無償化。「子育て世帯だけど、うちは対象になるの?」「どんな風に申請するの?」など、いまさら聞けない疑問がある方も多いのではないでしょうか。我が家も、娘は無償対象の年齢ではないものの、今後関係のある制度。今回は、幼保無償化について徹底的に調べてみました。
幼保無償化法案の背景
もともと、2017年12月に「新しい政策パッケージ」の「人づくり改革」の一環として盛り込まれていた「幼児教育の無償化」がもとになっています。
子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の
引用:「新しい経済政策パッケージ 平成 29 年 12 月8日」
無償化を一気に加速する。広く国民が利用している3歳から5歳までの全ての
子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf
さらに、2019年の5月「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 」が交付され、その中の基本理念をもとに「幼児教育、保育の無償化(幼保無償化)」が実施されることになりました。
1.基本理念
引用:https://www.cao.go.jp/houan/doc/198_1gaiyou.pdf
子ども・子育て支援の内容及び水準について、全ての子供が健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであることに加え、子供の保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮されたものとする旨を基本理念に追加する。
幼保無償化の基本内容
幼保無償化は、全ての3歳以上の未就学児が対象。幼稚園月々の限度額があるものの、これまで世帯収入などによって保育料が決まっていた保育所、認定こども園などは完全に無料になるのが嬉しいですね。
また、0〜2歳児の場合、非課税世帯のみ保育所、認定こども園が無料になります。ひとり親世帯など、産後すぐ子どもを預けて働きたいものの、保育料の負担が厳しい世帯の負担が減りますね。
幼保無償化の対象施設と各施設の違いって?
保育の無償化の対象施設、対象サービスは様々。無償化の範囲や申請方法などの本題に入る前に、保活経験なしの方にもわかりやすいように、まずは対象施設、サービスの違いを見ていきましょう。
| 幼稚園 | ●幼児を保育しつつ、年齢に応じた環境で心身の発達を助長し、 教育する施設。 | 3〜5歳 |
| 保育所 | ●一般的に「認可保育園」と呼ばれる施設。 広さや、職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等、国の定めた基準をクリアした上で、都道府県に認可された施設のこと。 これに対し、基準を満たしていない施設が「認可外保育園」と呼ばれる。 ●目的は教育ではなく「保育」。 | 0〜5歳 |
| 認定こども園 | ●幼稚園と保育園、両方の特徴を併せ持ち、保育と教育を一体的に行う施設。 ●保育と教育を行う単一の施設として「認定子供園」とする『幼保連携型』。 幼稚園が保育所のような預かり型をする『幼稚園型』。 保育所が幼稚園的な機能をそなえた『保育所型』。 幼稚園でも保育所でもない地域の教育・保育施設がこども園の機能を果たす 『地方最良型』の4タイプがある。 | 0〜5歳 |
| 地域型保育 | ●0〜2歳児を対象に、地域の保育の需要に対応し、 待機児童の解消に務める保育施設のこと。 ●具体的には小規模保育施設(定員6〜19名のきめ細かい保育) や事業所内保育事業(企業が従業員の子供や地域の保育が必要な 子どもを受け入れる施設)。 | 0〜2歳 |
| 企業主導型保育事業 | ●企業が、0〜5歳までの自社の社員の子どもを受け入れ保育を行う施設。 ●事業所内保育事業との違いは、対象年齢や、地域の認可を受けず、 利用者との直接契約であることなど。 | 0〜5歳 |
| 認可外保育施設 | ●国が定めた設置基準を満たしていない、もしくは満たしているが 申請していない「認証保育所※」以外の保育施設。 ●認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッターなど。 | 0〜5歳 |
用語MEMO
※「認証保育所」・・・・・・東京都が独自に設定した基準による、新しい方式の保育施設。
幼保無償化の内容と対象者って?
おもな対象施設の「幼保無償化」の条件と上限、申請方法
ここまでは、「幼保無償化」の対象施設とその違いについておさらいしました。これらの対象施設は、それぞれ「無償化」に当たって細かい条件や上限があります。その違いを表にまとめて見ました。
| 対象 | 無償の上限 | 無償にならない費用 | 申請方法 | |
| 幼稚園 | 3〜5歳 | 対象となる幼稚園は無料。それ以外の幼稚園は「保育料+入園料(入園初年度に限り)」が月額25,700円まで無料 | 通園送迎費、食材料費、行事費等※1 | 園に申請 |
| 保育所 | ①3〜5歳 ②0〜2歳(住民税非課税世帯のみ) | 月額保育料がすべて無料 | 通園送迎費、食材料費、行事費等※1 園長保育料 | 不要 |
| 認定こども園 | ①3〜5歳【1号認定】 ②3~5歳【2号認定】 ③0~2歳【3号認定】(住民税非課税世帯) ※4 | 月額保育料がすべて無料 | ①通園送迎費、食材料費、行事費等※1 ②、③通園送迎費、食材料費、行事費等※1 園長保育料 | 不要 |
| 幼稚園の預かり保育※2 | 保育所、認定こども園等を利用できていない3〜5歳 | 幼稚園保育料の無償上限である、月額25,700円+月額11,300円の月額37,000円まで無料 | かかった預かり保育料以外の費用 | 園から「保育の必要性」認定の申請書を受け取り、自治体に提出。 |
| 認可外保育施設、ベビーシッター※3 | ①3~5歳 ②0〜2歳(住民税非課税世帯) | ①月額37,000万円まで無料 ②月額42,000万円まで無料 | かかった利用料以外の費用 | 自治体から「保育の必要性」認定の申請書をもらい、就労証明書やマイナンバーなど必要書類とともに、役所や施設などに申請(※個人の状況により申請場所は異なる) |
| 障害児通園施設 | 3〜5歳 | 月額保育料がすべて無料 (幼稚園は月額25,700円まで無料) | 医療費、食費など利用料以外の費用 | 不要 |
用語MEMO
※1食材料費については、「年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除」
「全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除」
※2幼稚園の通常預かり時間外で園で預かってもらうこと。夕方以降の時間や長期休み中の預かりなど。
※3都道府県に届出を出し国が許可した施設、事業者。
※4
【1号認定】・・・満3歳以上、就学前で2号認定以外の子供
【2号認定】・・・満3歳以上、就学前で保育の必要性が認められる子供
【3号認定】・・・満3歳未満、就学前で保育の必要性が認められる子供
「保育の必要性の認定」とは?
預かり保育や、認可外保育施設での無償化の条件にあるのが「保育の必要性の認定」という言葉。これはいったいどういう意味なのか、また認定にはどんな条件があるのかを調べて見ました。
新制度における「保育の必要性」の事由
○以下のいずれかの事由に該当すること
※同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合、その
優先度を調整することが可能①就労
引用「内閣府」:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/setsumei5.pdf
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時
預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している
親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利
用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
内閣府の資料によると、上記の項目のどれかに当てはまる世帯が「保育の必要性」があると認められるようです。比較的多そうなパターンとしては、「共働きのために保育園に預ける」「二人目の出産のために上の子を幼稚園に預ける」などが該当しそうですね。
住民税非課税世帯とは?
0〜2歳までの無償化に関わる条件が、「住民税非課税世帯」。これは、簡単にいうと所得が低い世帯です。自分の家庭が住民税非課税世帯かどうかは、自治体によっても基準が異なります。
【モデルケース】
①会社員、専業主婦、子ども一人の三人家族で年収205万以下
②会社員、専業主婦、子ども2人の4人家族で年収255万円以下
となります。
幼保無償化のデメリットや注意点
給食費は無償化対象外
無償化の対象は、保育料のみになります。通園送迎費、食材料費、行事費等はもちろん、保育園の延長保育費は対象範囲外。
これにより、これまで2号認定(満3歳以上、就学前で保育の必要性が認められる子供)の給食費は主食のみの負担でしたが、無償化後は、おかず・主食ともに全ての給食費が自己負担になります。
無償化によって給食費値上げの動きが想定されるため、結果的に自己負担額が大きくなるという可能性もあるので注意が必要ですね。
幼稚園の上限額問題
「無償化」と謳いつつも、完全無償ではないところがこの新制度の注意点。
国の認定を受けていない幼稚園は、「保育料+入園料(入園初年度に限り)」が月額25,700円までしか無料にならないという上限があります。
これにより何が起こるかというと、幼稚園の月額の引き上げ。SNSなどでは、無償の上限額を差し引いても、無償化以前よりも高額になる例も報告されています。
このため、保育園や認定こども園への入所希望が殺到し、激戦区はますます保育園に入りづらくなるということが予想されているので、手放しで喜べない側面もあるのが現実です。
待機児童問題の解決にならない
幼保無償化は待機児童問題の直接の解決策にはならないのが現状。利用料が無料になって申込者が増えても、その分保育施設や人手が増えなければ受け入れは滞ったままになります。
待機児童問題に対する現実的な対策として、無償化よりも保育施設を増やして欲しい!という声もちらほら聞こえます。
外国人学校は無償化の対象外
「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 」による基本理念では、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」という一文があるにも関わらず、国内の外国人学校は無償化の対象外という判断に、驚きや怒りの声があがっています。
その理由は「(これらの学校に)幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく、多種多様な教育を行っているため」というものでしたが、多様性が求められる社会でなぜ「多種多様な教育」が対象外になるのか、その理由が明確でないことに、さらに疑問の声が広がっています。
デメリットや注意点まとめ
✔︎給食費は無償化対象外
✔︎幼稚園の上限額があることによって、利用費の引き上げや保育所やこども園への入所希望が殺到
✔︎待機児童問題の解決にならない
✔︎外国人学校は無償化の対象外
【まとめ】幼保無償化の今後に期待!
10月1日からスタートする保育無償化。
共働きやひとり親家庭が増える一方で、待機児童問題や保育士の不足が深刻化する今の日本。幼保無償化のスタートによって、簡単に解決する問題ばかりではありませんよね。この新制度が第一歩となって、国民の声をより現実的に救いとった解決策が出てくることを、ひとりの母親として願っています。

幼保無償化によって、浮いたお金を教育資金に回す世帯も多いかと思いますので、近々ジュニアニーサや学資保険についての記事もアップしたいと思います!おたのしみに!








新着記事